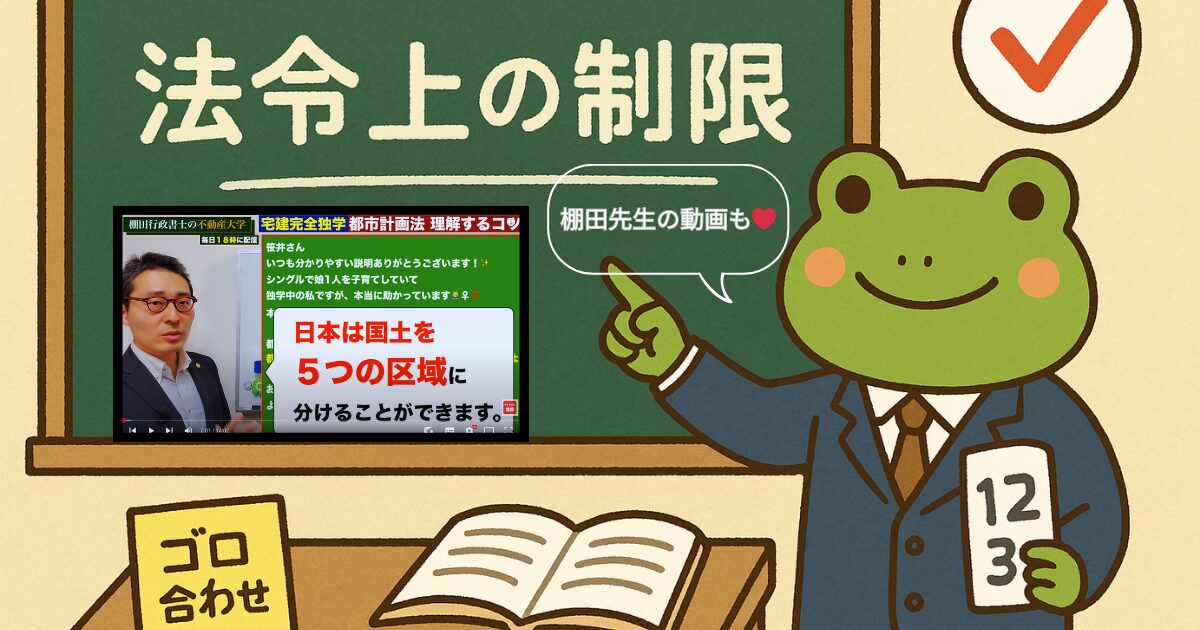はじめに
宅建試験の中でも「法令上の制限」は、覚える内容が多く苦手にする人が多い分野です。
しかし、毎年 8〜10問前後 出題されるため、避けては通れません。
今回は、この「法令上の制限」を効率よく覚えるためのコツをまとめます。
法令上の制限は「分野ごと」に整理して覚える
法令上の制限は、大きく分けると以下のようなテーマがあります。
- 都市計画法(用途地域、建ぺい率・容積率など)
- 建築基準法(道路・高さ制限・防火地域など)
- 農地法(権利移転や転用許可)
- 国土利用計画法(届出の要否、面積基準)
- 宅地造成等規制法(造成許可)
- 土地区画整理法(換地・保留地)
- 自然公園法・自然環境保全法 など
👉 まずは「どの分野の話なのか?」をパッと見て判別できるように整理しましょう。
数字は「ゴロ合わせ」で覚える
法令上の制限では「面積」や「高さ」など数字の暗記が必須です。
例:
- 国土利用計画法の事後届出 → 市街化区域 2,000㎡以上
- 農地法の許可 → 3条は権利移転、4条は転用、5条は転用+権利移転
- 建築基準法の接道義務 → 原則 幅員4m以上
数字はゴロ合わせや自分なりの語呂を作ると記憶に残りやすいです。
(例:にせん(2000)市街地に似てる! と覚えるなど)
過去問で「数字の使われ方」を確認
テキストで覚えても、実際の試験では「微妙な数字の違い」を問われます。
👉 過去問を解くことで「この数字はこう聞かれるんだ」という出題パターンが見えてきます。
イメージで覚える
例えば建築基準法の「道路に2m以上接していなければならない」は、家の前に車が入れないと困る…とイメージすると忘れにくいです。
また、用途地域も「住宅街に工場はダメ」「商業地域は建物が高くてもOK」と考えれば理解しやすくなります。
まとめ
- 分野ごとに分けて整理する
- 数字はゴロ合わせで暗記
- 過去問で出題パターンを確認
- イメージで理解する
法令上の制限は、最初は難しくても「繰り返す」ことで必ず得点源になる分野です。
数字や法律用語に慣れて、試験本番でしっかり点を取れるようにしましょう💪✨