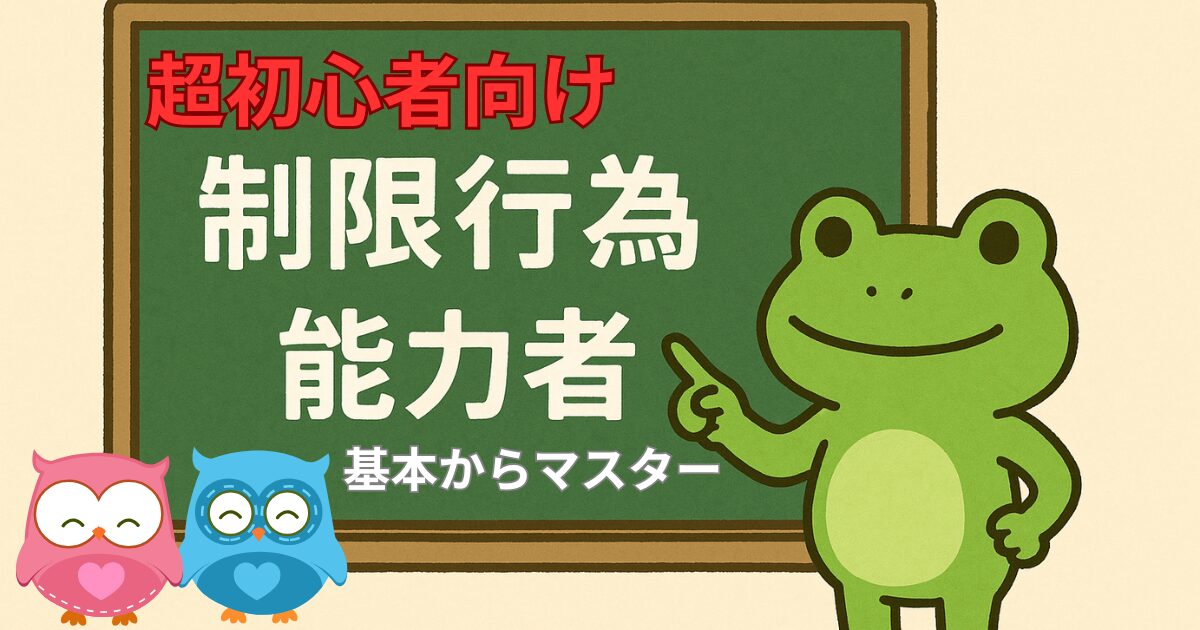宅建試験の「権利関係」分野の中でも、毎年のように出題されるのが【制限行為能力者】です。
未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人など、それぞれの「法律行為の有効・無効」の違いを整理しておくことが得点アップのカギになります💡
今回ご紹介する動画は、棚田先生の「制限行為能力者」解説講義です。
図や具体例を使いながらわかりやすく説明してくださっているので、苦手意識のある方もスッと理解できる内容になっています。
動画はこちら:
この動画で学べるポイント
- 制限行為能力者とは何か
- 各区分(未成年者・被後見人・被保佐人・被補助人)の違い
- 試験で問われやすい「取消し」「追認」のポイント
- 出題パターンとひっかけ問題の注意点
宅建試験対策のコツ
制限行為能力者の問題は、条文を暗記するよりも「どの人が、どんな法律行為をできるのか?」を表で整理するのがコツです。
特に「単独でできる行為」と「同意が必要な行為」を区別できるようにしておきましょう✍️
最後にひとこと
この分野は最初はややこしく感じるかもしれませんが、一度整理して理解すれば、毎年安定して得点できる分野になります。
棚田先生の動画を活用して、苦手意識を得点源に変えていきましょう💪